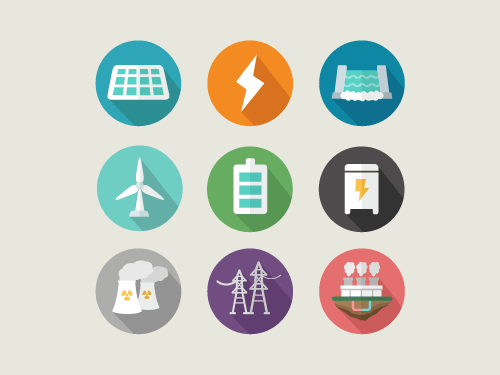業務コンサルタントとして培った業務分析・改善のスキル、部門横断のファシリテーション力、KPI設計力は、サステナビリティ・ESG(環境・社会・ガバナンス)コンサルタントにおいても大いに活かすことができます。企業の持続可能性や非財務情報開示の重要性が高まる中、ESG対応は経営課題の中核となっており、実務視点と変革力を併せ持つ人材が求められています。本記事では、業務コンサルタントからESGコンサルタントへ転職するためのステップ、必要なスキル、志望動機と職務経歴書の記載例をご紹介します。
目次
- 1. 業務コンサルタントとESGコンサルタントの違い
- 2. 活かせるスキルと経験
- 3. 転職を成功させるステップ
- 4. 求められる知識と補完方法
- 5. 職務経歴書の記載例
- 6. 志望動機の記載例
- 7. まとめ
1. 業務コンサルタントとESGコンサルタントの違い
| 項目 | 業務コンサルタント | ESGコンサルタント |
|---|---|---|
| 目的 | 業務の最適化・効率化 | 非財務情報の整備と企業価値向上 |
| 領域 | 業務プロセス、組織、IT | 環境、人的資本、ガバナンス、開示 |
| 成果物 | 業務改善提案書、業務要件定義書 | ESGマテリアリティ分析、開示支援、サステナ戦略 |
2. 活かせるスキルと経験
- 業務の可視化・プロセス設計スキル
- KPI設計やモニタリングフレームの構築
- ESG課題に対する構造的アプローチ
- 非財務情報の定量化・評価フレーム活用力
- 部門横断の合意形成・ステークホルダーマネジメント
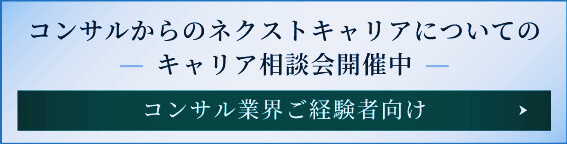
3. 転職を成功させるステップ
- ESGの主要基準と潮流を学ぶ:TCFD、GRI、ISSBなどの開示基準
- コンサル経験の“非財務的意義”を棚卸し:人的資本や業務の持続性に関わる改善提案
- ESGスコアやマテリアリティマトリクスに慣れる:企業の統合報告書を読み込み、分析視点を養う
- 志望動機では“社会と企業の両立支援”を明示:サステナ視点の定着・実装支援を担いたい想いを伝える
4. 求められる知識と補完方法
- TCFD、GRI、ISSB、CDP等の国際基準
- サステナビリティ経営指標(GHG排出量、人的資本指標等)
- 統合報告・マテリアリティ特定手法
- 非財務情報の定量化手法、BIツール活用
- 参考書籍:『ESG経営の実践』『統合報告書の読み方』
5. 職務経歴書の記載例
氏名:佐藤 絵里 生年:1990年生まれ ■職務要約: 業務コンサルタントとして約8年間、業務改善、KPI設計、業務可視化に従事。近年は人材活用やガバナンス領域の改善提案も担当し、人的資本や非財務指標に基づく支援を推進。今後はESG領域に軸足を移し、企業のサステナビリティ経営支援に貢献したいと考えている。 ■職務経歴: ○○コンサルティング株式会社(2016年4月〜現在) ・大手製造業:人的資本マネジメント支援、開示指標策定 ・小売業:ESG KPIモニタリング設計・人事部門への導入支援 ・ESGワークショップ(GRI準拠)運営・資料作成 ■保有資格: ・中小企業診断士 ・GRI認定サステナビリティレポーティング研修修了 ・TOEIC 880点 ■学歴: 一橋大学 商学部 卒(2013年3月)
6. 志望動機の記載例
業務コンサルタントとしての業務改善・可視化の経験を通じて、業務の効率化だけでなく、企業の中長期的な価値創造に資する視点の重要性を強く意識するようになりました。ESGや人的資本など、非財務情報が企業経営に不可欠となる中で、実務的な導入支援に挑戦し、社会的価値と企業価値の両立に貢献したいと考えております。
7. まとめ
業務コンサルタントの経験は、サステナビリティ・ESG領域においても非常に有効です。実務視点で課題を可視化し、構造的に改善していくアプローチは、非財務情報の整備・活用においても大いに求められています。今後、企業価値の根幹を支える役割として、ESGコンサルタントはますます重要性を増していくでしょう。
関連動画(Youtubeチャンネル)
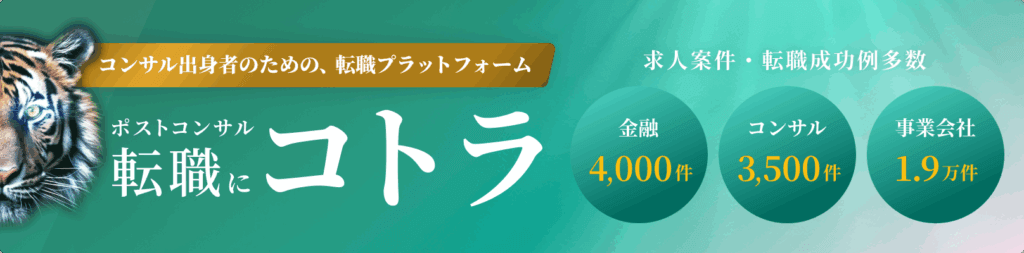
ESGコンサルタントの最新求人情報
- サステナビリティコンルタント(プロダクト・ポリシー・キャピタル)/戦略コンサルティングファーム/年収:~1600万円/東京都
- プロジェクトマネージャー(サステナビリティ開示Saas)/ESGテックベンチャー/年収:~800万円/お問い合わせください。
- ESG情報開示支援SaaSプロダクトのエンタープライズセールス/ESGテックベンチャー/年収:~800万円/東京都
- 【2月21日(土) 1Day選考会】サステナビリティ・コンサルタント/監査法人グループのリスクアドバイザリー/年収:~1600万円/東京都
- 流通促進セールスマネージャー/急成長中のブランドコンサル企業/年収:~1400万円/東京都
- サステナビリティ戦略コンサルタント/日系戦略・業務コンサルティングファーム/年収:1000万円~1400万円/東京都
- サステナビリティ推進担当/経営コンサルティング会社/年収:~1000万円/東京都
- サステナビリティスペシャリスト/外資系不動産ファンド/年収:1000万円~1400万円/東京都
- 社会課題解決型コンサルティングファームでの事業プロデューサー(ソーシャルデザイン事業部)/年収:~1000万円/東京都
- サステナビリティ コンサルタント/CO2排出量見える化・削減クラウドサービス提供企業/年収:~1200万円/東京都
この記事を書いた人
コトラ(広報チーム)
金融、コンサルのハイクラス層、経営幹部・エグゼクティブ転職支援のコトラ。簡単無料登録で、各業界を熟知したキャリアコンサルタントが非公開求人など多数のハイクラス求人からあなたの最新のポジションを紹介します。