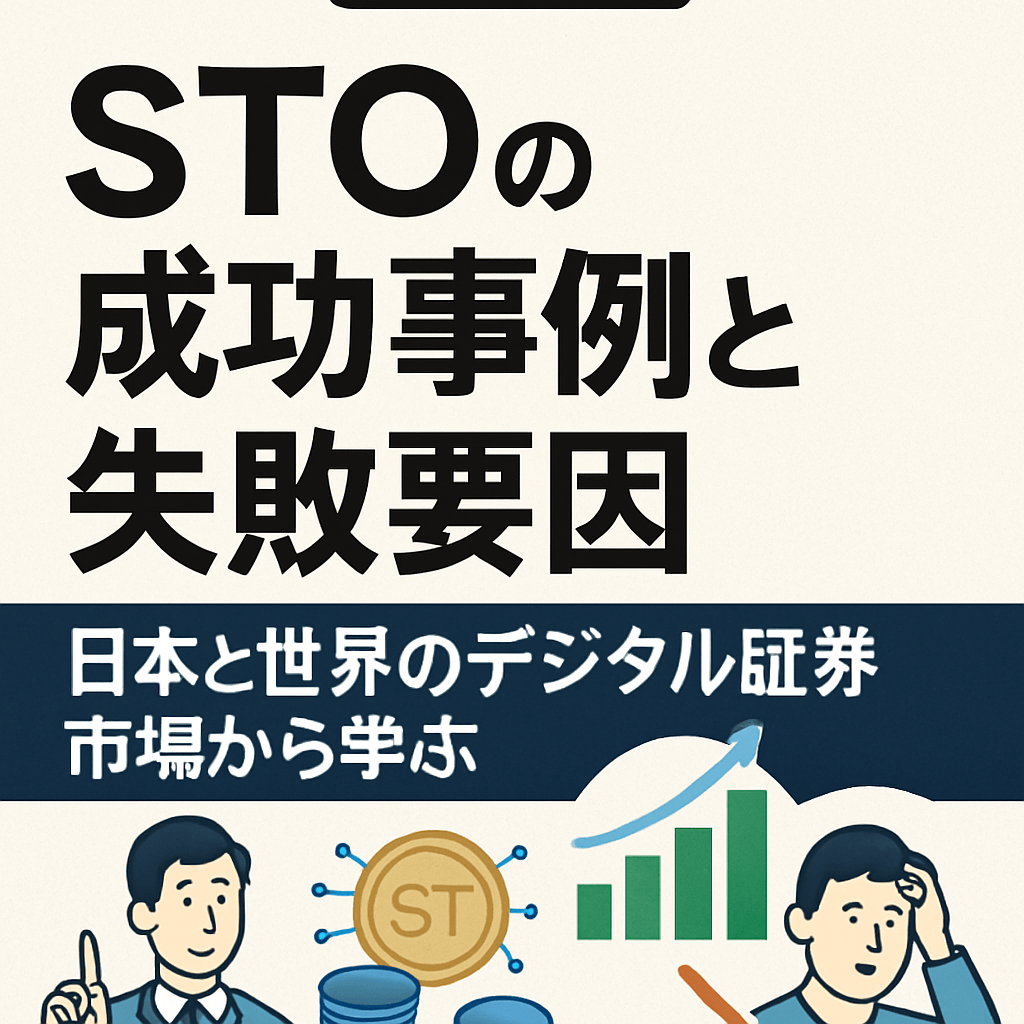STO(セキュリティトークン・オファリング)とは?目的と可能性
セキュリティトークン・オファリング(STO:Security Token Offering)は、ブロックチェーン技術を活用して株式・債券・不動産などの有価証券をデジタル化し、発行・流通させる仕組みです。
透明性の向上、取引コスト削減、少額投資の実現など多くのメリットが期待される一方、規制や市場インフラ整備の課題から、成功と失敗の事例があります。
本記事では、日本と海外におけるSTOの事例を整理し、金融業界が注目すべき成功要因・失敗要因をわかりやすく解説します。
海外のSTO成功事例と規制の枠組み
米国のSTO事例と規制(Regulation)の活用現状
米国では、STOはSEC(Securities and Exchange Commission: 証券取引委員会)の厳格な規制枠組みの下で実施されており、特に以下の3つのRegulation(規制)が主要な道筋となっています。
Regulation D(Reg D)
適格投資家を対象とした非公開の募集・私募を可能にします。発行額に上限がない代わりに、一般投資家へのプロモーションは制限されます(Rule 506(c)を除く)。
最も一般的に利用される規制枠組みであり、特にプライベート・エクイティや不動産ファンドのトークン化に用いられます。
Regulation S(Reg S)
米国外の投資家を対象とした証券発行を可能にし、米国の証券法上の登録義務が免除されます。米国企業が海外からの資金調達を行う際や、グローバルなSTOにおいて利用されます。
Regulation A+(Reg A+)
発行額に上限(Tier 2で年間$7,500万)があるものの、一般投資家からも資金調達が可能です。公開企業のような情報開示が求められますが、IPO(新規株式公開)に比べて手続きは簡素化されています。中小企業が一般投資家を巻き込みながら、比較的少額の公募を行う場合に適しています。
成功事例の共通点と課題
成功事例には、投資家保護と法的遵守を徹底するための共通要素が見られます。
適格投資家を対象とした発行
規制対応が比較的容易なRegulation Dなどを活用し、豊富な資金を持つ機関投資家や適格投資家をターゲットとすることで、初期の資金調達を成功させています。
ブローカーディーラーを介したKYC/AML体制
KYC(Know Your Customer: 本人確認)とAML(Anti-Money Laundering: マネーロンダリング対策)は、証券取引の基盤です。SECに登録されたブローカーディーラーを介することで、これらの規制要件を確実に満たしています。
ATS(Alternative Trading System)を活用した二次市場
トークンの流通・売買の場として、SECに登録されたATSを利用することで、合法的な二次流通市場を提供し、投資家に対し流動性の確保を図っています。
課題点
成功事例が限定的である主な要因として、以下の点が挙げられます。
二次市場の流動性不足
ATSの整備が進んでいるものの、従来の証券市場と比較すると参加者や取引量がまだ少なく、トークンの流動性(換金性)が低い状況が続いています。
高コスト構造
法的・技術的な要件を満たすためのブローカーディーラーやATSの利用、厳格な監査とコンプライアンスの維持は、発行体にとって大きな高コスト要因となっています。
ヨーロッパ・アジアの制度モデルと成功例
欧州やアジアの一部の国々では、既存の金融規制を活用しつつ、デジタル証券特有のガイドラインやサンドボックス制度を導入することで、STOを積極的に推進しています。
スイス:銀行主導と既存法制への統合
スイスは、暗号資産やブロックチェーン技術に対する寛容な姿勢で知られる「クリプト・バレー」の中心地です。 FINMA(Financial Market Supervisory Authority: 金融市場監督機構)が、トークンを「支払い、資産、ユーティリティ」の3種に分類するガイドラインを早期に公表し、特に資産(セキュリティ・トークン)には既存の証券法を適用する方針を明確にしました。
成功事例としては、銀行が積極的にデジタル証券の発行に関与し、トークン化された債券や株式の発行が実現しています。これは、伝統的な金融機関がデジタル証券市場の信頼性を高めている成功例です。
ドイツ:伝統的証券市場との統合
ドイツは、デジタル証券を既存の金融法制に統合するアプローチでSTOを推進しています。BaFin(Federal Financial Supervisory Authority: 連邦金融監督庁)は、デジタル債券の発行を可能にする法改正を推進し、デジタル証券の法的確実性を高めました。
成功事例としては、BaFinの承認に基づき、不動産や企業向けの債券型STOが実現しています。特にブロックチェーン技術を利用した電子証券の発行は、ペーパーレス化と効率性向上という点で伝統的な証券市場との統合が進むモデルケースとなっています。
シンガポール・香港:規制サンドボックスによる実証
アジアの金融ハブであるシンガポールと香港は、国際的な資金を取り込むための環境整備に注力しています。MAS(Monetary Authority of Singapore: シンガポール金融管理局)やSFC(Securities and Futures Commission: 証券先物委員会)は、規制サンドボックス(Regulatory Sandbox)を通じて、新しい技術を用いた金融サービスの実証実験を積極的に支援しています。
成功事例としては、クロスボーダー型STOの活発化と資産のトークン化が挙げられます。サンドボックス内で、異なる国の投資家を対象としたクロスボーダー型のSTOの実証が活発化しており、地域外の投資家資金を効率的に取り込み、アジアにおける国際的な資金調達手段としての地位を確立しつつあるのです。
海外のSTO成功事例は、厳格な法的遵守と伝統的な金融インフラ(銀行、ブローカーディーラー、ATS)との連携が不可欠であることを示しています。
米国が適格投資家を主な対象とすることで実績を積み上げる一方、欧州・アジアは既存の法制への統合や規制サンドボックスを通じて、国際的な流動性と効率性の向上を目指しており、課題である流動性の不足と高コスト構造を克服することが、STO市場のさらなる成長の鍵なのです。
日本国内のSTO事例と課題
2019年に成立した「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」による金融商品取引法の改正(2020年5月1日施行)において、セキュリティトークンは法令上「電子記録移転有価証券表示権利等」および「電子記録移転権利」という枠組みで位置づけられました。
具体的には、有価証券をトークン表示させることで、電子情報処理組織を用いて移転できる財産的価値を有する権利として、従来の有価証券規制の対象となることが明確化されました。
一方、株式型STO(未上場株式などを対象とするトークン化案件)については、現状で公開されている案件数が少なく、発行体にとっては規制対応コスト(法務・開示体制・証券取引業登録等)や、流通性を確保できるセカンダリーマーケットの整備が未成熟であることが障壁となっているという報告があります。
これらを踏まえると、日本STO市場の主な課題は以下の三つに集約できます
・発行コストの高さ:STO案件では、技術実装(ブロックチェーン・スマートコントラクト・台帳管理)、法務・コンプライアンス(開示要件・登録・監査)、プラットフォーム設計など、従来の証券発行以上に初期固定費および維持コストがかかる
・投資家層の限定性:多くの案件が富裕層・機関投資家あるいは私募型で実施されており、最低投資額や募集方法が一般投資家の参加を限定するものが多い。一般投資家向け・少額投資型案件は増えてきてはいるが、まだ数少ない
・セカンダリーマーケット(流動性)の未整備:発行後に売買が活発に行われるプラットフォームが十分そろっていないこと、売買手続き・価格評価の透明性・取引コスト等の面で未整備な点が多い。これにより、投資家が保有後の出口戦略を立てにくい状態になっている
STOの失敗要因 ― 海外と日本に共通する課題
デジタル証券市場の成長を阻害している共通の課題は、主に以下の4点に集約されます。
規制の不確実性:法整備が不十分、または短期的な変更がリスク
STOは、新しい技術と既存の法律の境界線上にあるため、法的リスクが常に伴います。トークンが「有価証券」に該当するかどうかの判断基準が、特に国境をまたぐ場合や新しいスキームの場合に、いまだ明確でないことがあるのです。
新技術に対する当局の理解が深まるにつれ、規制が急に変更・厳格化されるリスクもあり、進行中の案件の前提が崩れたり、すでに発行されたトークンの法的安定性が損なわれたりする可能性があります。
こうした不確実性から、発行体は高額な法務・コンプライアンス費用をかけざるを得ず、これがSTOの高コスト構造の一因となっています。
二次市場の流動性不足:売買機会が乏しく、投資家魅力が低下
流動性は金融商品の生命線です。現状、STの取引は厳格な規制のもと認可を受けた取引プラットフォームに限定されているため、既存の株式や債券に比べて売買が困難です。そのため参加者も少なく、取引量が希薄なのです。
また、買い手と売り手の提示価格の差(スプレッド)が広がりやすく、投資家は適正価格での売却が難しいと感じます。投資家は「いつでも換金できるか」を重視しており、流動性が低いSTは、特に個人投資家や短期の機関投資家にとって魅力が低下し、新規資金の流入が停滞します。
インフラの信頼性不足:発行・保管・決済を担う基盤が不十分
ブロックチェーン技術を利用したインフラが、伝統的な金融市場の要求水準に完全に達していないことも要因の一つです。デジタル証券の安全な保管(カストディ)を担う、高度なセキュリティと監査体制を持つ専門業者がまだ不足しています。
現段階では、証券と資金の交換を同時に行うDVP(Delivery Versus Payment)決済を、法定通貨建てで安定的に、かつ効率的に行うためのブロックチェーン上の仕組み(アトミック・スワップなど)が、各国で検証段階にあります。発行に用いられるスマートコントラクトのバグや、基盤となるDLT(分散型台帳技術)の障害、サイバーセキュリティリスクなど、懸念点がいくつも存在するのが現状です。
投資家教育不足:リスク理解の浸透不足により市場拡大が停滞
新しいテクノロジーと法制度を組み合わせた商品であるため、投資家側の理解が追いついていないことも挙げられます。STが単なる「暗号資産」ではなく、「規制された有価証券」であることを正確に理解している投資家がまだ少数派なのです。
上記を踏まえ、STO市場を成功させるには、規制の明確化と予見可能性を確保し、発行体が安心して参入できる法的基盤を築くことが不可欠です。同時に、技術的リスクを含む透明性の高い情報開示を徹底し、投資家保護を優先する必要もあります。
また、取引プラットフォームの拡充と国際連携により、二次市場の流動性を確保し、投資魅力を高めた上で、安全な取引となるよう、インフラの信頼性を確立することが重要です。
これら明確な制度、流動性、信頼性が揃うことで、デジタル証券市場の信頼性と拡張性が担保されるでしょう。
日本市場の展望と政策提言
日本は、金融商品取引法の改正によりデジタル証券の法的枠組みを整備した先進的な国の一つです。さらなる市場拡大のためには、具体的にどのような政策提言が必要になるのでしょうか。
税制整備:キャピタルゲイン課税やクロスボーダー取引における課税ルールの明確化
STの売却益に対するキャピタルゲイン課税について、既存の有価証券と同様の扱いとするかどうかの明確な指針が必要です。クロスボーダー取引における源泉徴収や租税条約の適用など、複雑な国際取引の課税ルールを早期に明確化し、海外投資家の参入障壁を取り除く必要があります。
事業者基準の拡充:証券会社以外の事業者参入を可能にし、市場競争を促進
現在、STO関連事業の多くは、高度なライセンスを持つ金融商品取引業者に限定されています。技術力を持つフィンテック企業やIT企業の参入を、適切な監督の下で可能にすることで、競争を促進し、インフラの多様化とコスト低減を図るという方法も一つです。
国際的互換性の確保:シンガポール・スイス等と調和した制度整備
日本独自の規制を設けるだけでなく、シンガポール、スイス、米国といったSTO先進国の規制や技術標準と相互運用性(インターオペラビリティ)を持つ制度設計を目指す必要があります。これにより、グローバルな投資資金を日本市場に取り込みやすくなります。
投資家保護と技術革新の両立:スマートコントラクト監査や新技術の制度取り込み
STの権利を規定するスマートコントラクトについて、第三者による監査や技術基準を設けることで、投資家が技術的なリスクを負うことを防ぐことができます。また、規制サンドボックスなどの仕組みを継続的に活用し、DAOやDeFiといった新技術がもたらす革新を、投資家保護を損なわない範囲で柔軟に制度に取り込むことが重要です。
まとめ:デジタル証券市場でのSTO活用に向けて
STOは、日本の資本市場に新たな成長機会をもたらし、不動産・未公開株・インフラといった非流動資産の市場拡大につながる可能性を秘めています。
一方で、成功には規制整備・市場インフラ・投資家教育が欠かせません。
海外事例が示すように、明確な制度と流動性確保が市場拡大の鍵であり、日本も国際的な視点を持って取り組む必要があります。
コトラでは、STO人材を募集する求人を広く取り扱っています。未経験で採用している企業もありますので、ぜひ御覧ください。