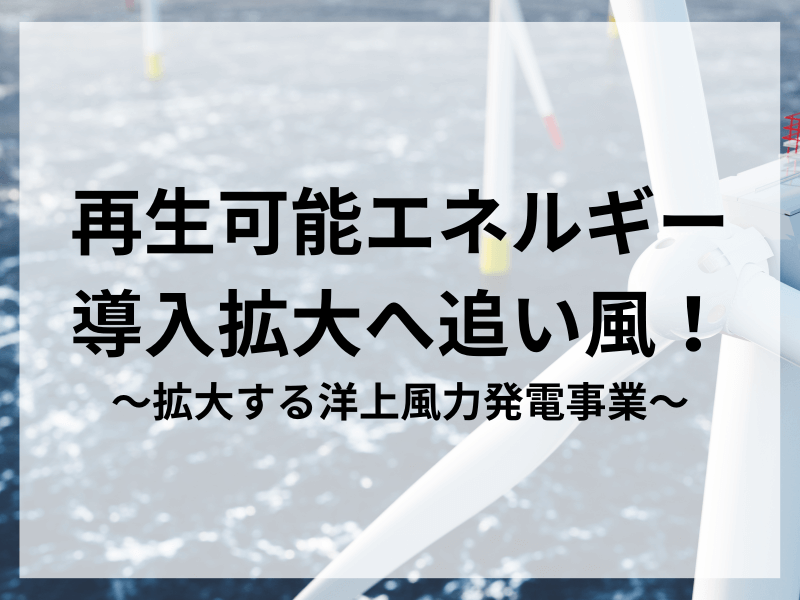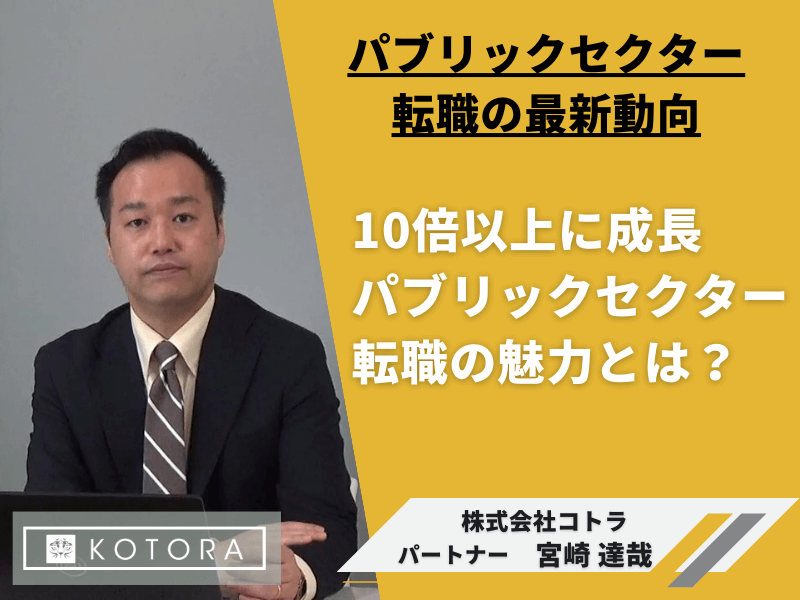官民連携(PPP)や民間資金活用による公共施設整備(PFI)といったパブリックセクターのプロジェクトは、社会課題解決と経済合理性を両立する取り組みとして注目を集めています。市場調査や政策分析の経験を持つリサーチ・アナリストにとって、こうした分野は次なる活躍の場となり得ます。本記事では、リサーチ・アナリストがPPP/PFI領域へとキャリアチェンジするためのステップ、必要なスキル、志望動機と職務経歴書の記載例を解説します。
目次
- 1. リサーチ・アナリストとPPP/PFI業務の違い
- 2. 活かせるスキルと経験
- 3. 転職を成功させるステップ
- 4. 求められる知識と補完方法
- 5. 職務経歴書の記載例
- 6. 志望動機の記載例
- 7. まとめ
1. リサーチ・アナリストとPPP/PFI業務の違い
| 項目 | リサーチ・アナリスト | PPP/PFIコンサルタント |
|---|---|---|
| 目的 | 業界・政策・市場分析と助言 | 公共インフラ整備における民間活用支援 |
| 成果物 | レポート、分析資料 | 事業スキーム、収支試算、VFM分析、提案書 |
| ステークホルダー | 企業、行政、研究機関 | 中央省庁、自治体、民間事業者、金融機関 |
2. 活かせるスキルと経験
- 定量・定性データに基づいた政策分析力
- 社会課題や行政施策への関心と理解
- 複数利害関係者との調整・提案スキル
- ファクトベースでの報告書作成力
- 法制度や補助金制度に関する情報収集力
3. 転職を成功させるステップ
- PPP/PFIの基礎理解:PFI法、VFM、契約スキーム、SPCの仕組みを学ぶ
- 公共政策・財政制度の学習:地方創生、国土強靭化計画、補助金交付要綱の構造理解
- 実績と接点の棚卸し:政策調査・自治体向け案件・官民連携分析など
- 志望動機に公共性を組み込む:社会課題への貢献意識を明文化
- 案件ベースの理解を深める:過去のPFIプロジェクト(学校、公園、下水道など)を調査
4. 求められる知識と補完方法
- PPP/PFIの契約・事業スキームに関する知識
- 公共調達、コンセッション方式、VFM分析手法
- 地方自治体の意思決定プロセス
- 行政計画と関連法規(PFI法、地方自治法など)
- 関連教材:国土交通省ガイドライン、JAPPP研修、自治体職員向け資料
5. 職務経歴書の記載例
氏名:佐々木 翔 生年:1989年生まれ ■職務要約: 政策系シンクタンクにて約9年間、リサーチ・アナリストとして中央省庁・自治体向けの政策調査、事業評価、費用対効果分析に従事。公共事業の評価やPPP/PFI事例分析を通じて、政策の立案・実行支援に携わる。今後はより実務的に公共インフラ整備の推進に貢献したく、PPP/PFI分野のコンサルタント職を志望。 ■職務経歴: 株式会社◯◯シンクタンク(2014年4月〜現在) ・自治体の公共施設再編計画策定支援(施設統廃合、財政影響分析) ・中央官庁向けPPP導入に関する定量調査 ・PFI導入可能性調査におけるVFM分析、収支シミュレーション担当 ・教育・下水道・庁舎分野の実証実験プロジェクトに参画 ・自治体ヒアリング、住民説明会用資料の作成 ■保有資格: ・PPP/PFI実務者研修修了(JAPPP) ・行政書士試験合格 ・日商簿記2級 ■学歴: 東北大学 経済学部 卒(2012年3月)
6. 志望動機の記載例
これまで政策系シンクタンクにて、官民連携に関する調査・提案を数多く担当してまいりました。実際のPFI案件に携わる中で、制度面だけでなく現場での実行支援に深く関与したいという思いが強まり、実務ベースでのPPP推進に携われるコンサルタント職を志望いたしました。貴社においても、分析力と調整力を活かして、自治体・民間双方にとって持続可能な事業スキームの構築に貢献したいと考えております。
7. まとめ
リサーチ・アナリストとしての定量分析力、政策理解力、資料作成能力は、PPP/PFIの実務において極めて有効な基盤です。あとは制度や事例を学び、実務に応用するだけです。公共性の高いプロジェクトに参画し、社会インフラの未来を支えるキャリアへの第一歩を踏み出してみませんか?