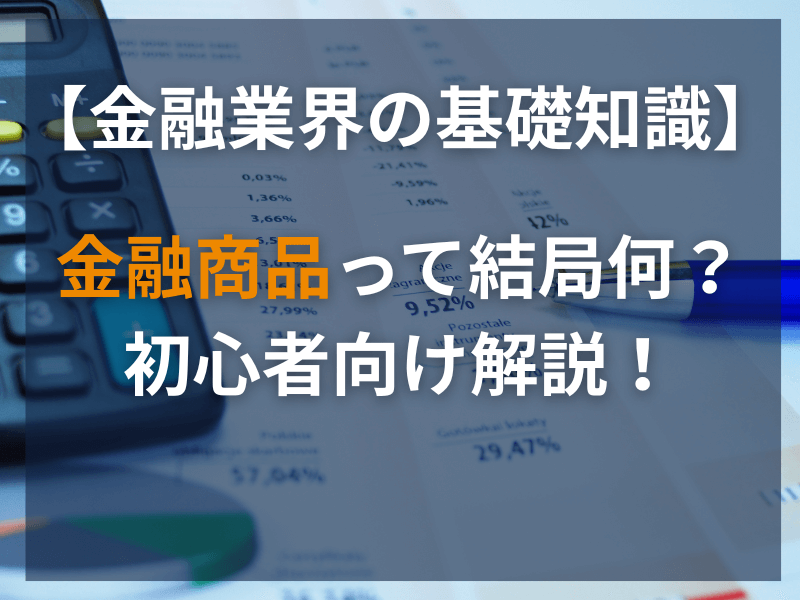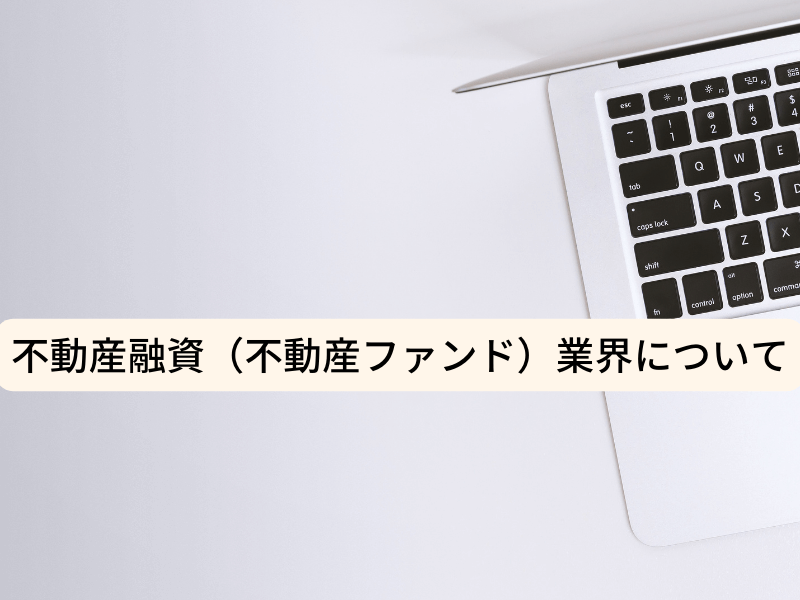金融商品は、その仕組みやリスク、収益構造の違いによって多様な特徴を持ちます。預貯金のような安全性重視の商品から、株式や投資信託、債券、さらには金やFXといったリスクを伴うものまで、選択肢は広がる一方です。本稿では、金融業界の基礎知識として、代表的な商品について解説します。
金融商品一覧
預貯金(普通預金・定期預金)
預貯金は、銀行や信用金庫にお金を預ける最も基本的な金融商品です。普通預金口座に預け入れた資金はいつでも引き出しが可能であり、利息はほとんど付きません。一方、定期預金は一定期間資金を拘束する代わりに、普通預金より高めの金利が設定される場合があります。
どちらも元本保証があり、万一金融機関が破綻した場合でも、預金保険制度によって、1人あたり1,000万円までの元本とその利息が保護される点が大きな特徴です
外貨預金
外貨預金は、米ドルやユーロなどの外国通貨で資金を預ける商品です。円預金と異なり、預入時と払戻時の為替レート差によって為替差益・差損が生じます。また、預け入れ時と引き出し時には為替手数料(買値と売値の差であるスプレッドに含まれることが多い)もかかるため、為替変動リスクとコストの両方を考慮する必要があります。
債券(国債・社債)
債券は、発行体にお金を貸し付ける証書のようなもので、発行体が支払う利息(クーポン)と満期時の元本返済を受け取ることができます。国債は政府が発行するため信用度が高いのに対し、社債は企業が資金調達のために発行するものです。企業の信用リスクが伴いますが、国債より高い利回りが期待できることが特徴です。買付を行う際には、金利が上昇すると債券価格は下落し、金利が下落すると債券価格は上昇するという金利変動による価格変動リスクや、発行体の信用状況(信用リスク)を把握することが重要になります。
以下に、種類ごとの特徴をまとめました。
- 国債
- 日本国債:日本政府が発行。利回りは低水準だが、信用度が高いため国内機関投資家を中心に広く購入されている。短期(割引国債)、中長期(利付国債)など期間も多様。
- 米国債・その他先進国国債:米ドル建て国債は流動性が高く、グローバルマネーの運用先として重要。外国為替リスクを伴うものの、分散投資の一環として組み入れられる。
- 地方債
- 普通地方債:都道府県や市町村など地方公共団体が発行。プロジェクト資金の調達が目的で、地方財政の健全性によって利回りが異なる。
- 特別地方債:上下水道や交通公共事業など、特定用途の返済財源が定められているため「目的税方式」とも呼ばれる。
- 普通地方債:都道府県や市町村など地方公共団体が発行。プロジェクト資金の調達が目的で、地方財政の健全性によって利回りが異なる。
- 社債
- 普通社債:企業が資金調達のために発行。格付け会社の評価(AAA~BBなど)によって利回りが左右され、一般に国債より高いクーポンが設定される。
- 劣後債:破綻時の返済順位が普通社債より後になる分、より高い利回りが期待できる一方、信用リスクも大きい。
- 転換社債(CB):満期前にあらかじめ定められた株式に転換できる権利付き。株価上昇時のキャピタルゲインと債券の安定収益を両取りできる可能性がある。
- 普通社債:企業が資金調達のために発行。格付け会社の評価(AAA~BBなど)によって利回りが左右され、一般に国債より高いクーポンが設定される。
- 外債
- 現地通貨建外債:外国企業・政府が現地通貨で発行。利回りは高いものの為替リスクが大きく、新興国国債では政治リスクも考慮が必要。
- 外国政府保証債:政府保証付き国債など、万一発行体が債務不履行に陥っても別の機関が保証するタイプがあるが、市場では限られた銘柄しか流通しない。
- 現地通貨建外債:外国企業・政府が現地通貨で発行。利回りは高いものの為替リスクが大きく、新興国国債では政治リスクも考慮が必要。
株式
株式は企業のオーナーシップの一部を購入するもので、株価の変動や配当を通じてリターンを得ることができます。企業業績や市場環境に応じて株価は日々変動しており、企業分析や決算書の読み方、業界トレンドを追うことで値動きの背景を理解しやすくなります。また、株主総会やIR(投資家向け広報)活動にも関わるため、企業のガバナンスや広報戦略に触れたい人の関心も集める商品です。
投資信託
投資信託は、多くの投資家から集めた資金をまとめて運用会社が株式や債券などに投資し、その成果を投資家に還元する仕組みです。小口資金で幅広い資産に分散投資ができ、個別銘柄の選定や運用は専門家が行います。運用管理費用(信託報酬)が年率で発生し、元本保証はありませんが、運用手法やファンドの構成を選ぶことで目的に合わせたポートフォリオを組むことができます。
投資信託は、「オープン型」と「クローズド型」に大別され、それぞれ運用方法や取引形態に特徴があります。
・オープン型投資信託
目論見書で運用方針やコスト構造を確認し、株式型・債券型・バランス型(株式と債券を組み合わせ)など、リスク許容度や投資期間に合わせたファンドを選択します。随時買付・随時解約が可能で、いつでも口数を増減できます。
・クローズド型投資信託(私募ファンド等)
一定期間の運用を前提に募集が行われ、満期(償還)まで追加購入や解約が原則できない商品です。ヘッジファンドやプライベートエクイティファンドなど、高度な戦略やレバレッジ運用を行うものも含まれ、プロ投資家向けの商品設計が多い点が特徴です。
個人型確定拠出年金(iDeCo)
iDeCoは、自分で掛金を拠出し、年金として受け取るための私的年金制度です。掛金は全額が所得控除の対象となるため節税効果があり、運用益は非課税で再投資され、受取時も公的年金等控除や退職所得控除の対象となるなど、一定の税制優遇があります。
一方で、原則として60歳まで資金を引き出せないため、長期的な視点で加入条件や運用商品を選ぶ必要があります。年金商品の中でも税制設計や運用商品のラインナップが業者ごとに異なるのが特徴です。
貯蓄性保険(終身保険・個人年金保険など)
貯蓄性保険は、死亡保障や疾病保障といった保障機能に加え、契約時に定められた予定利率に基づいて保険料が運用され、解約返戻金や満期保険金(個人年金保険など)を受け取ることができる貯蓄機能を併せ持ちます。したがって、中途解約時の解約返戻金の推移を理解することが重要です。
外国為替証拠金取引(FX)
FXは、証拠金を担保にレバレッジをかけて通貨を売買し、為替差益を狙う取引です。24時間取引が可能で流動性が高い反面、自己資金を超える損失が生じるリスクもあります。証拠金維持率やロスカットルール、スワップポイントの仕組みを理解し、リスク管理手法や取引ツールの操作に精通しておく必要があります。
証拠金維持率(マージン・メンテナンス・レシオ)
FX取引では、まず担保として「証拠金」を口座に預け入れ、その証拠金を元にレバレッジをかけて通貨を売買します。証拠金維持率とは、保有するポジションに対して口座内に残っている自己資金(有効証拠金)がどの程度あるかを示す割合です。
- 有効証拠金:口座残高+評価損益+未受渡スワップポイント
- 必要証拠金:現在保有中のポジションを維持するのに必要な証拠金の合計
多くの国内FX業者では、この維持率が100%を下回ると「追証(追加証拠金)」の請求対象となり、さらに一定の下限(業者により異なるが、たとえば50%以下)を割り込むと強制的にポジションが決済されます。
ロスカットルール(強制決済ルール)
ロスカットルールとは、証拠金維持率があらかじめ定められた水準を下回った際に、損失の拡大を防ぐために業者が自動的にポジションを決済する仕組みです。
・トリガーライン設定
例として、証拠金維持率50%をロスカットラインと設定など
・アラート発動
維持率がトリガーラインを下回ると、発注システムから警告メールや画面通知が届く場合もある
・自動決済
複数のポジションがある場合は、含み損が大きい順に決済され、順次維持率を回復させる方式が一般的
ロスカットは発動と同時に「成行」注文で執行されるため、市場急変時には想定より不利な価格で決済される可能性がある点に注意が必要です。
スワップポイント(通貨間金利差調整額)
スワップポイントとは、取引対象となる二国間の金利差を日々調整するために必要となる費用または受取額です。
・算出の仕組み
- 基本金利差:高金利通貨(例:豪ドル)と低金利通貨(例:円)の短期金利差をもとに計算
- FX業者の調達コストや手数料を上乗せ/差し引き
- 取引量(ロット数)に応じて日次で口座に加減算
- 受け取り・支払いの区別
- 買いポジション(ロング):買った通貨の金利が売った通貨の金利を上回る場合、差額を受け取る
- 売りポジション(ショート):買いポジションと逆で、差額を支払う
- 買いポジション(ロング):買った通貨の金利が売った通貨の金利を上回る場合、差額を受け取る
- 実務上の留意点
- 祝日や週末をまたぐと、スワップ調整が3日分まとめて反映される「三日分スワップ」タイミングがある
- 業者によって提示レートや付与タイミングが異なるため、長期保有を前提とする場合は業者比較が重要
- 祝日や週末をまたぐと、スワップ調整が3日分まとめて反映される「三日分スワップ」タイミングがある
金(ゴールド)投資
金地金・金貨・金ETFなどでの金投資は、インフレや市場混乱に対する安全資産として注目されています。株式や債券と相関が低いとされ、ポートフォリオの分散効果を高める役割を果たしますが、金自体は利息や配当を生まないため、価格変動によるキャピタルゲインのみがリターン源となります。
金は「実物保有」と「金融商品を通じた保有」があり、投資目的やコストに応じて選択肢が分かれます。
・実物保有(地金・金貨):地金(インゴット)は、純度99.99%など一定規格のものが流通しています。記念金貨・投資用金貨については、収集価値(プレミアム)が付きやすく、地金価格に対して上乗せコストが高くなる傾向があります。
・金ETF・金投資信託:金ETFは、証券取引所に上場しており、株式と同じようにリアルタイムで売買できる点が大きな特徴です。実際の金地金は信託銀行などが厳重に保管しており、投資家は現物管理の手間を省けます。一方、非上場の金投資信託は、販売会社を通じて申込単位で取引し、最低1万円程度から始められるものが多いですが、信託報酬はやや高め(年率0.2~0.5%)に設定されています。
どちらも金価格に連動したリターンを目指しますが、ETFは流動性と透明性、投資信託は積立や複合運用の柔軟性がそれぞれの強みです。
・金先物・金ミニ取引:取引所(TOCOMなど)で金を将来受け渡す契約を売買します。証拠金取引のためレバレッジを効かせられ、価格変動を利用した短期売買に適しますが、保有コストや追証リスクも伴います。
不動産投資
不動産投資は、賃貸用のマンションや商業ビルなどを購入して賃料収入や売却益を得る仕組みです。立地・物件の管理状態・マーケット動向など多くの要素が収益に影響します。ローン金利や修繕費用、税務の扱い(減価償却など)を理解し、キャッシュフロー計算や収支シミュレーションを行う知識が求められます。
不動産市場に間接的に参加できる「金融商品」としては、主に以下の3つがあります。
・REIT(不動産投資信託)
不動産投資信託は、多数の投資家から集めた資金をオフィスビルや商業施設、物流施設などの不動産に分散投資し、その賃料収入や売却益を投資家に分配する仕組みです。株式市場に上場している上場REITは、株式と同様に証券取引所で売買できるため流動性が高く、小口資金で不動産市場にアクセスできます。
・不動産ファンド(私募ファンド)
主に機関投資家向けに組成されるプライベートファンドで、大型商業施設やホテル、物流施設などに投資します。上場しない種類のため流動性は低いものの、プロの運用チームが厳選した物件を対象とし、長期的に賃料収入とキャピタルゲインを目指します。
・不動産クラウドファンディング
小口投資家が少額から参加できる仕組みで、インターネットを通じて集合的に不動産案件へ出資します。募集スキームには「不動産特定共同事業(匿名組合方式)」や「ソーシャルレンディング型」のものがあり、各案件ごとに想定利回りや運用期間が提示されます。直接物件を所有しないため、物件管理の手間はなく、少額で不動産の収益に参加できる点が特徴です。
おわりに
金融商品はそれぞれ異なるメカニズム、内在するリスク、そして収益構造を有しており、自身の資産運用目標やリスク許容度に基づいた戦略的な選択が不可欠です。各商品の特性を深く理解し、常に最新の市場動向、税制・規制の変革、そしてマクロ経済のトレンドを注視することで、最適化された資産運用ポートフォリオの構築が可能となります。
金融業界でのキャリアを志向される方々にとっても、金融商品の基礎知識は業界構造を理解するための第一歩です。この基礎知識を深化させることで、ポートフォリオマネジメントや金融商品の開発、セールス等、様々なキャリアを歩むことができます。
弊社では、様々な専門性を活かせる多様な求人を取り扱っています。
キャリアアップや金融業界への転職をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
- 大手証券会社での取引法務担当(金融商品組成に係る法務や契約対応等)※Senior Associate / Vice President/年収:~1200万円/東京都
- グローバルバンクでのプロダクトアナリスト/年収:~1600万円/東京都
- ストラクチャード・ファイナンス格付アナリスト/年収:800万円~1200万円/東京都
- 大手証券会社での金融商品に係る評価、リスク分析業務/年収:~1200万円/東京都
- グローバルバンクでのクオンツ(市場系金融商品の評価・リスク管理モデル開発)/年収:800万円~1800万円/東京都
- ユニコーン企業への投資プラットフォームを運営する企業での金融商品組成におけるプロジェクトマネージャー/年収:800万円~1400万円/東京都