
ご経歴の概要
コトラ 馬場:
まずは、皆様のご経歴についてお聞かせください。
植地様:
私は元々、銀行でキャリアをスタートさせまして、その後ビジネススクールを経て、戦略系コンサルティングファームに入りました。
その後、アメリカのプライベートエクイティ(以降「PE」)にて、3年ほどGPの仕事に従事した後、2009年にアリックスパートナーズに参画しました。
バイスプレジデントとして入社して、あらゆる案件に携わらせてもらいました。
全社的な業績改善という共通項はありますが、業界は、小売から金融機関、消費財メーカーなど製造業まで幅広く携わることができました。
元々PE出身だったため、PEの投資先の会社を担当したことも非常に多かったです。その他、不正調査のメンバーとして従事していた時期がありました。
海外プロジェクト経験としては、1年以上にわたり、東南アジアの航空会社のターンアラウンドに参画いたしました。また、東南アジアのノンバンクのターンアラウンドも担当しました。
その後、2019年に一度アリックスパートナーズを離れ、コンサルティングファームにて4年半勤務した後、2023年に再び当社に復帰しました。現在は、日本オフィスの代表と同時に、TMTセクターのリーダーの役割も担っています。
鈴木様:
私は三菱商事で勤務した後、ビジネススクールに進学し、帰国後、日系コンサルティングファームで4年半ほど業務経験を積みました。
2012年にアリックスパートナーズに入社し、今年(2023年)で12年目を迎えます。
アリックスパートナーズにはアソシエイトとして入社し、社内のプロモーションを経て、MDを務めています。
現在はPEのアジアのリーダーと、自動車製造業の日本のリーダーの役割を担っています。
ユニークなプロジェクトとしては現場の経営陣の一員として1年3ヶ月ほどの間、赤字経営の会社を立て直すプロジェクトに携わったことがあります。5年近く赤字が続いていた企業様でしたが、半年で単月黒字、1年で年間黒字を達成しました。
主に、事業再生、コスト削減、事業のカーブアウトなどのPE関連の案件を担当していました。
海外の案件も多く、アメリカの収益性が悪化した事業の再生、中国の工場の立て直しなど、グローバルの案件も少なくありませんでした。
木村様:
私は今年(2023年)アリックスパートナーズに参画しました。大学卒業後は、戦略系コンサルティングファームに就職し、20代を過ごしました。その後、30代で事業会社に転じ、モバイル系のゲーム会社、外資系の製薬企業、国内のスタートアップなど、様々な業界で経験を積みました。
当社に入社する前は、4年弱、日本の独立系PEに在籍しました。投資先の会社にCFO兼CSOとして入り、投資先のPMIやバリューアップに携わりました。プロ経営者の方と共に、コロナ禍の困難な状況下で、全社改革を推進しました。
アリックスパートナーズに参画してからは、PEのクライアントを担当し、投資先のDDなどをやっています。日本オフィスでは消費財と小売領域も担当しています。
コトラ 馬場:
植地様、木村様の共通点として、PEを経験されたということですが、PEからアリックスパートナーズへのご転職に至った背景についてお伺いしてもよろしいでしょうか。
植地様:
私が在籍していたPEで、アリックスパートナーズに依頼して、大規模なターンアラウンド案件をやったことがありました。
フードパッケージの会社で、短期間で数百億円規模の在庫削減や、最大顧客との取引の解消など大胆な施策を実行しました。その結果、急ピッチでキャッシュを創出し、その年のTurnaround of the yearに選ばれました。
当時、私はその案件の一環として、その会社の子会社売却を担当しておりました。それが最初のアリックスパートナーズとの出会いです。
私がいたPEファンドが日本からの撤退を決めた際に、そのファンドはまだアリックスパートナーズと取引がありましたので、紹介していただいたという経緯です。
木村様:
私が在籍していたPEは、ポートフォリオとディールのチームが分かれておらず、ソーシングからディールエグゼキューション、バリューアップまで一連の業務を行っていました。ある案件で、私は投資先企業のCFO兼CSOとして派遣されました。
PEは株主としてガバナンス機能を果たしながら企業価値を向上させる役割を担っていますが、私はその役割も担いつつ、実際に執行側に入りターンアラウンドにも携わりました。両方の立場の経験から、企業価値を向上させることの面白さややりがいを実感しました。そのため、PEからアリックスパートナーズへのキャリアを選択しました。
また、アリックスパートナーズは、ミッドキャップから大企業まで、幅広い規模の企業を対象としている点も魅力でした。
コトラ 馬場:
鈴木様のご入社のきっかけもお伺いできますでしょうか。
鈴木様:
前職でも企業再生案件に携わり、企業再生の道を更に極めたいと考え、再生系のコンサルティングファームを探しました。
当時は比較的小規模のファームでしたが、非常に優れた成果を上げていることを知りました。アリックスパートナーズの『企業再生プロフェッショナル』(下記書籍)という本を読み、企業再生のアプローチや案件のレベルの高さに感銘を受けました。
当時アリックスパートナーズはJALの案件に携わっており、その案件はまだ公表されていなかったのですが、海外では非常に有名であり、日本に進出してビジネスを開始したばかりのタイミングであったため、ぜひ入社したいという強い想いを抱きながら面接に臨んだ記憶があります。
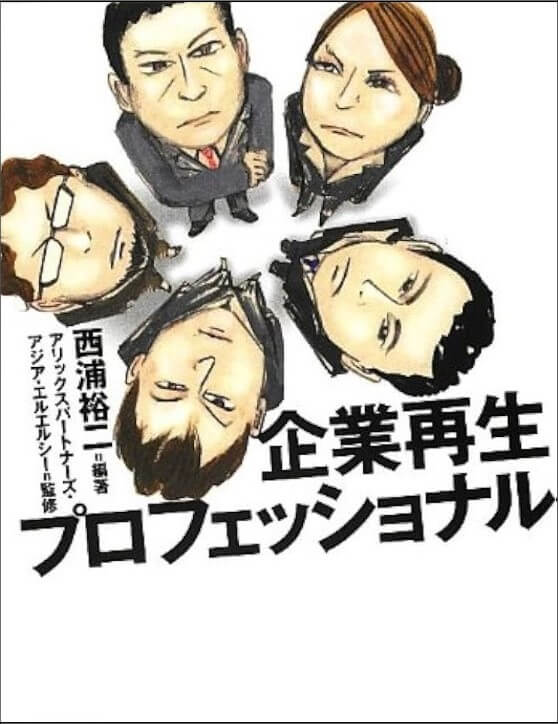
西浦 裕二【編著】/アリックスパートナーズ・アジア・エルエルシー【監修】(2012/08発売)
アリックスパートナーズならではの魅力
コトラ 馬場:
他のコンサルティングファームとの違いについて教えていただければと思います。
植地様:
1つ目は、短期間で抜本的な改革を成し遂げられるコンサルティング会社を目指しています。
業績が悪化している企業、既に持ち直したものの更なる成長を目指す企業など、短い時間軸で抜本的にいろいろ変えて、PLもBSも抜本的にステップチェンジを成し遂げたいと思っています。
我々は、ホームドクターのようにクライアントと長期間付き合いながら、経営上の課題を解決するようなスタイルではありません。我々のクライアントは、火事場のような状況に陥っていることが多いため、課題を解決したら、一旦終了し、次の現場に移るというスタイルになります。
2つ目は働き方についてですが、基本は常駐型になります。
最初の診断から施策の実行、そして成果発現に至るまで、マネージャー以下のメンバーが常駐し、クライアントとワンチームとなって取り組んでいます。
その過程で、弊社のメンバーが要所要所に座り、クライアント企業に特定の業務の適任者がいない場合は、本部長や社長、CFOを務めることもあります。
このように、クライアントと一体となって改革を進めていく点が、特徴の一つと考えています。

3つ目は、グローバルに展開するコンサルティングファームとして、グローバリティを重視している点です。
日本オフィスを大きくすれば、自社だけで対応できることも増えるでしょうが、アリックスパートナーズの場合は、ほぼ全ての案件で海外オフィスと協働しております。
グループ全体で3,000人以上いますが、クライアントのニーズに合わせて、必要な専門性やリソースをグローバルで調達し、切れ目なくサービスを提供できる体制を整えています。
鈴木様:
少し補足させていただくと、他のコンサルティングファームと異なる点として、レポートを提出するだけでなく、その提言を実際にPLやBSに結びつけるという点が最も異なると考えています。
実際に収益性を改善することが我々のバリューです。そのために我々はハンズオンで現場に入り、現場のオペレーション改善など、BS、PLの改善にコミットしています。
このようなスタイルを実現するために、豊富な経験とスキルを有するシニアメンバーが必要で、MBA卒や大学新卒の方が多数在籍するようなピラミッド型の組織構造は採用していません。
我々は必要に応じて、暫定経営陣としてクライアントに関わることもあり、そういった点が一番の違いとして挙げられます。
木村様:
私自身、戦略ファームでの経験はありますが、アリックスパートナーズはPL/BSにコミットしているからこそ、スピード感があると感じています。
重要な局面でPL/BSを改善するために入っているため、常にタイムイズマネーという状況に置かれています。
そのため、圧倒的にスピードが速いです。クライアントにとっての重要な局面は、数年に一度、あるいは十年に一度など各クライアントによって変わりますが、我々は長年取り組んでいますので、ファーム全体で高度な専門知識を培っています。
その専門性を活かし、いかに早く実行して結果を出すかという点が他社と圧倒的な違いと考えています。
植地様:
「タイムイズマネー」とも言いますが、「タイムイズエネミー」とも考えています。
時間が経てば経つほど、事業を毀損していくこともあるため、その間に我々はできるだけ手を打っていく必要があり、売上が1兆円を超えるような企業であっても、4週間から6週間で一旦プロジェクトの初期診断を終わらせてしまいます。
そのため、粗さが残ってしまうこともしばしばあるのですが、6〜7割正しければそれでいきます。
「これは取り組みが必要な事項である」と特定すると、そこから実行にギアチェンジしていく、そこのスピード感はだいぶ違うと思います。
案件へのアサインは、同じような状況を経験したことがある人をあてがっていきます。
基本的に「こういう状況であれば、このように課題を解いていく」という答えが見込めた状況から入っていくため、仮説思考がより精鋭化していると感じます。
コトラ 馬場:
他のコンサルティングファームと比較して、一つの案件当たりの人数に違いはあるのでしょうか。
鈴木様:
ひとつの案件あたり、大体3人から4人くらいが平均的です。
シニアのプロジェクトマネージャー、その下に2人メンバーがついて、3人で回していくケースが多いです。
そこにクライアント企業の方々が、それぞれ課題ごとにつくという形で、クライアントと一緒にチームを組成していく点が、他のファームとの一番の違いかと思います。
他社ファームだと、プロジェクトマネージャーやチームメンバーがいて、我々がクライアントの皆様に担っていただく部分も自分たちの会社でやってしまいます。そうすると、そのコンサルファーム自体の知見は深まると思いますが、肝心なクライアントは知見が深まらない。
我々はクライアントと一緒に働くことにより、クライアント自体の知見を深め、ともに成長していくことを重視しています。
我々の介入がなくても、自走できる体制を作っていくことが、クライアントにとってベストであるという考えを持っているため、その部分をブラックボックスにするようなことは一切しません。
一緒に改革を行い、その次世代の経営者を育て、サポートする、そういう考え方で取り組んでいます。
サービスの特徴・強み
コトラ 馬場:
クライアントに提供するサービスの特徴や強みについて教えてください。
植地様:
アリックスパートナーズの提供する主要なサービスは、企業再生、包括的な業績改善です。
企業再生では、再建計画を作っていく立案、ステークホルダー間の合意形成、キャッシュを創出する支援、暫定経営陣の派遣等に取り組み、包括的な業績改善においては、売上成長、プライシング、営業効率化、コスト削減、直接費用・間接費用・人件費などに取り組みます。さらに、バランスシートによって、ワーキングキャピタル(運転資金)改善によるキャッシュの創出も提供するサービスの一つです。
このほか、リスクアドバイザリー(エコノミックコンサルティング、不正調査、移転価格など)、デジタル(Cyber DD、リスク評価、デジタル戦略など)、コーポレートストラテジー&トランスフォーメーション(リーダーシップ開発、組織改革など)までにサービスを拡大しています。
鈴木様:
我々はPEのサポートが非常に多く、それに伴いM&Aのサービスのサポートで、DDのタイミングから、クローズ後のバリューアップの支援が多くなります。
植地様:
スピードとインパクトを考えると、PEと、最近のエンゲージメントファンドと親和性が非常に高く、そこに関する投資先への支援は極めて多いです。
求める人物像
コトラ 馬場:
求める人物像、ターゲットをお伺いできますか。
木村様:
結果にコミットするという弊社の特徴から、結果ドリブンの方や自ら進んで行動するマインドセットを持つ方です。また、スピードが非常に大事であるため、スピード感をもって取り組める方が大前提になります。
比較的小規模のチームですが、ファーム全体でナレッジを活用していくため、チームワークとリーダーシップを大事にしていただきたいと思います。
リーダーシップというのは自分で全てやることではなくて、チーム全体として何かを成し遂げようということです。そういった点を大切にできる方に入社していただきたいです。
植地様:
アントレプレナーシップを持つ方が良いです。小規模なチームで、あれこれ自ら工夫して解決しなければならないことが多いため、そのような状況を楽しみながら取り組める人が求められます。
併せてコモンセンスも重要です。会社の方を説得して物事を進めていくときの根拠が、自身の常識やフェアネスとなるため、その点がきちんとしている人が良いと感じています。
さらに、ハンズオンできちんと手が動く人です。MDであっても、手を動かすことを楽しむことが必要です。
複雑な状況やコンフリクトが発生した際に、クライアントに対して厳しい意見を述べながらも、コンフリクトを恐れない姿勢は非常に重要です。
鈴木様:
以前、『やり抜く力 GRIT』という本が流行ったことがあるのですが、決めたことをやり続けることができる人、ゴールのためにありとあらゆる努力をして根気強くやっていくマインドを持った人が非常に重要だと思います。
株主やマネジメントなど様々なステークホルダーがいるので、コミュニケーション能力が高いことも重要だと考えます。
また、セクター軸があり、何らかの機能軸を持っている人です。我々は「スパイク」と呼んでいるのですが、非常にコスト削減に強い、トップラインを伸ばすことに強い、サプライチェーンに強いなど、そういったようなスパイクを持っている方は我々としては非常に歓迎しています。
植地様:
大きくセクターと機能のマトリクスで考えていますが、セクターとしては自動車・製造業が一つ、そして電機メーカーに代表されるTMT、小売・消費財、あとはPEあたりが業界軸で、そのどこかに詳しい人はフィットします。
機能軸では、購買・サプライチェーン・生産などのオペレーション、組織、営業も含めた売上拡大、M&Aの4つがあります。業界軸と機能軸の4✕4くらいで、既存メンバーでカバーしにくい領域もあり、その領域が得意とする人を重点的に探しています。
候補者様へのメッセージ
コトラ 馬場:
御社を志望される方へのメッセージをいただけますでしょうか。
木村様:
私が入社した理由でもありますけど、世の中に対してインパクトを与えたい方、将来経営を目指す方にとって、非常に良い環境だと思います。
私も実際入社して驚いたのですが、本当にグローバルな環境です。日々、グローバルメンバーと話す機会がありますし、プロジェクトのアサインも東京だけではなくて、グローバルなアサインになります。
本当にグローバルな環境で働きたいと考えている方には、とてもいい会社です。
鈴木様:
紙のレポートだけを作っているプロフェッショナルの方が、そのレポートを使って、どうやって実際の現場を改善していきたいのか、会社全体をどう動かしていきたいのかといったようによりハンズオンにシフトされたい方には、ぜひ当社に応募していただきたいです。
日本のビジネスコミュニティの中でも、プロ経営者がだいぶ広まってきていますけど、プロ経営者になるための登竜門にも通じるものがあるので、将来は経営者になりたい方も応募をお待ちしています。
会社全体を見渡しながら仕事ができるので、特定の機能だけではなく、よりハイレベルな仕事をしてみたいという方にとっては、非常に良い環境になると思います。
我々の活動の一部として、暫定経営陣の派遣をやっています。私が一番最初に、暫定経営陣として派遣されたのは、アソシエイトのときでした。職位に関係なく、そういうチャンスを会社として提供してくれるので、会社経営を実際に経験してみたい、実際にラインに入って、どう会社を動かしていくのか経験したいとお考えの方へ、非常に良い環境が提供できると思います。
植地様:
私からは2点申し上げたいと思います。プロフェッショナルファームで知的に鍛えられた方とか、数字的なところを鍛えられた方とかがいますが、弊社は、そこを統合して、現場の状況に使えるスキルに再構成し直せるファームだと感じています。
あと一つは、弊社は驚くほどファミリー的な文化が強いです。
海外のオフィスも含めて、まだMDが300人弱しかおらず、顔が分かって繋がることが可能な規模感であり、何か聞きたいことがあれば、全世界にメールで質問して、エキスパートを見つけて相談しながら提案を進めていったり、デリバリーしたりという、グローバルにファミリーライクな文化です。
ご自身の成長をバックアップする雰囲気が非常にありますので、ご安心いただきたいです。
アリックスパートナーズにご興味がある方へ
今回特集しましたアリックスパートナーズ様の求人をご紹介します。
ご興味がある方は、下記ボタンよりぜひご応募ください。
■募集ポジション
コンサルタント、バイスプレジデント、シニアバイスプレジデント、ディレクター、パートナー
■役割概要
【企業再生】
・再建計画の立案/実行とステークホルダー間の合意形成
・キャッシュ創出・管理強化
・暫定経営陣の派遣
【包括的収益性改善】
・コスト削減(調達費、拠点再編、人員削減など)
・売上成長(プライシング、営業効率化、製品導入など)
・バランスシートの改善
【事業/業界再編】
・カーブアウトによるノンコア事業の切出し・売却
・企業買収による成長の加速・統合シナジーの創出
・合従連衡・垂直統合
上記のアリックスパートナーズの強みであるターンアラウンド&リストラクチャリング、業績改善の主要サービスのほか、リスクアドバイザリー(エコノミックコンサルティング、不正調査、移転価格など)、デジタル(Cyber DD、リスク評価、デジタル戦略など)、コーポレートストラテジー&トランスフォーメーション(リーダーシップ開発、組織改革など)の領域まで提供サービスは拡充している。
■コンサルタント、バイスプレジデント、シニアバイスプレジデントの要件
・論理的思考と分析能力
・現場で困難な改革をリードする実行能力
・学士号以上の学位
・ビジネスレベルの日本語力
・ビジネスレベル以上の英語力尚可
・コンサルティングファームにおけるプロジェクトマネジメント、クライアントマネジメントの経験尚可
・一定の業界あるいは機能領域の専門性尚可
■ディレクター、パートナーの要件
・コンサルティングファームにおけるプロジェクトマネジメント、クライアントマネジメントの経験
・一定の業界あるいは機能領域の専門性
・論理的思考能力と分析能力
・リーダーシップとチームマネジメント能力
・現場で困難な改革をリードする実行能力
・学士号以上の学位
・ビジネスレベルの日本語力
・ビジネスレベルの英語力尚可
コトラでは業界動向や今後のキャリアについて無料キャリア相談会を開催しております。
最新の採用動向や非公開求人情報などの情報提供をさせていただきます。
また、ざっくばらんな意見交換・ご相談をさせて頂きながら、理想のキャリアを歩むためのアドバイスをさせていただきます。 お気軽にご相談ください。
登壇者紹介
ゲスト
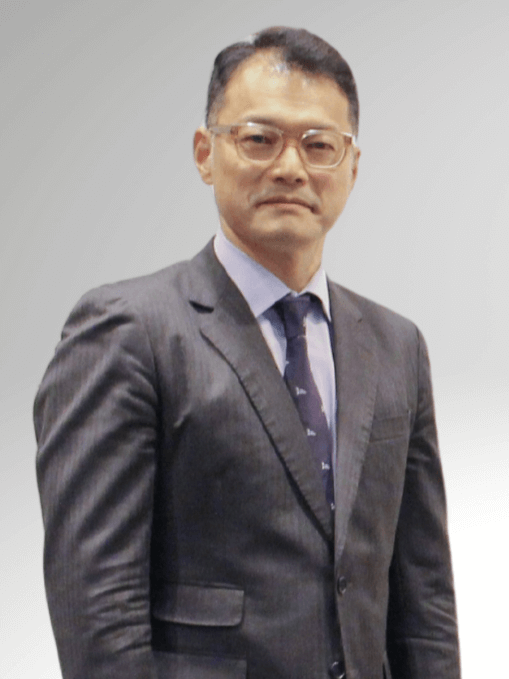
アリックスパートナーズ 日本代表
パートナー&マネージングディレクター
植地 卓郎 様

アリックスパートナーズ
パートナー&マネージングディレクター
鈴木 智之 様

アリックスパートナーズ
パートナー
木村 哲哉 様
インタビュアー

株式会社コトラ
エグゼクティブコンサルタント
馬場 大地
九州大学農学部卒業後、株式会社三井住友銀行にて法人融資業務を経験。金融教育事業でのマネジメント経験を経て、現職。
[ 担当業界 ]
PEファンド、不動産ファンド、総合商社、投資銀行、財務アドバイザリー(FAS)、戦略コンサル、大手銀行












